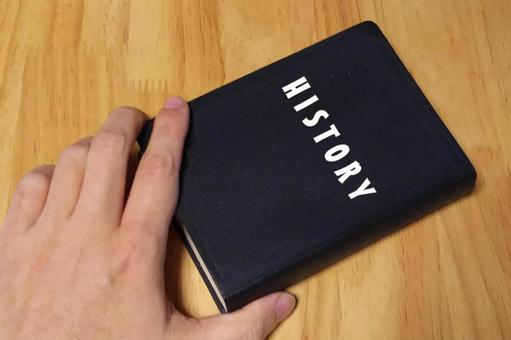公認会計士の受験時代、監査法人で務めている間、そして今も、
どんどん新しい会計基準が適用され、そのたびに必死でキャッチアップしてきました。
学んだ結果をアウトプットすることでわずかばかりでも
クライアントや周囲の皆様にお役立ちできていたと思うので、
何とか食らいつけて良かったと思っています。
それはそれでいいんですが、今改めて思うのが、
「今の会計基準の体系って過去どういう経緯をたどってきているんだろうか?」
ということです。
中学高校では日本史・世界史という形で、各国の歴史を学びますよね。
(それが正しく教えられているかはいったん置いておいて)
現在は過去からの積み上げなので、今を知るためには歴史を知らないとだめです。
会計って…その歴史を教わる機会ってありましたっけね?
足元の会計基準がどうなっているかを学ぶ機会は山ほどありますけど、
歴史となるとほぼ皆無だと思います。
モヤモヤっとしていた時に、こんな本を見つけました。

裏表紙を見てみると
「日本の会計基準はどこからやって来て、いまどこにいて、これからどこへ向かおうとしているのか。第Ⅰ巻は、戦後「企業会計原則」の公表以降、証取法会計における会計基準が確立された時期、概ね1980年代までを対象としている。会計基準の開発主体は企業会計審議会であるという既成概念に反して、大蔵省や日本公認会計士協会に注目し、その動向や国会審議等を素材として利用しつつ、日本の会計基準の実像「なぜその時期に、なぜその内容になったのか」を動的に解明する。」
とありました(全Ⅲ巻)。
まだ目次くらいしか目を通せていませんが、この切り口で
会計基準を読み解いている本ってまぁないと言っていいと思います。
貴重だ!と思ってⅢ巻まとめて衝動買いしてしまいました笑
著者の大日向隆(おびなた・たかし)氏は、東京大学経済学部経営学科卒業で、
現在は同大学の大学院経済学研究科准教授を務められているそうです。
「公認会計士等検索システム」にお名前はありませんでしたので、公認会計士ではないようですね。
目次をざっと見た範囲ですが、やはり基準が制定される背景には
国会でどういう点が議論されていたのかとか、大蔵省の動向とか、
そういったのもありそうですね。
基準を読むだけでは見えてこない部分であり、非常に興味深いです。
個人的には、なぜ日本はここまでIFRSに追いつけと言わんばかりに
IFRSへのコンバージョンを進めたのか、その辺りが気になっています。
時価会計が取り入れられることで日本の外資化が助長されたのではと
考えていますので。

今一度原点に返って会計の歴史を学んでみるのも楽しそうです。
~編集後記~
- 月次決算支援第2営業日目。慣れてきたということもあり順調で、かつ大きなイレギュラーもなく落ち着いていました。
- ライティングスキル向上のための「写経」を。試しにIPO実務検定HPのコラムを書き写してみることに。書くのは本当苦手なので手が疲れます…
- 夜は会計士の知り合いが幹事?をやっている飲み会に。1時間以上遅れてしまったのですが、美味しいお肉を堪能させていただきました。
- わかりづらいですが、なぜか冬用のあったかハウスがひっくり返った状態で暖を取るうちの猫

【SNS】フォローお願いします
- X(旧Twitter):会計・その他気づきの発信
- Instagram:日々の自己研鑽を発信
- note:旧ブログ。