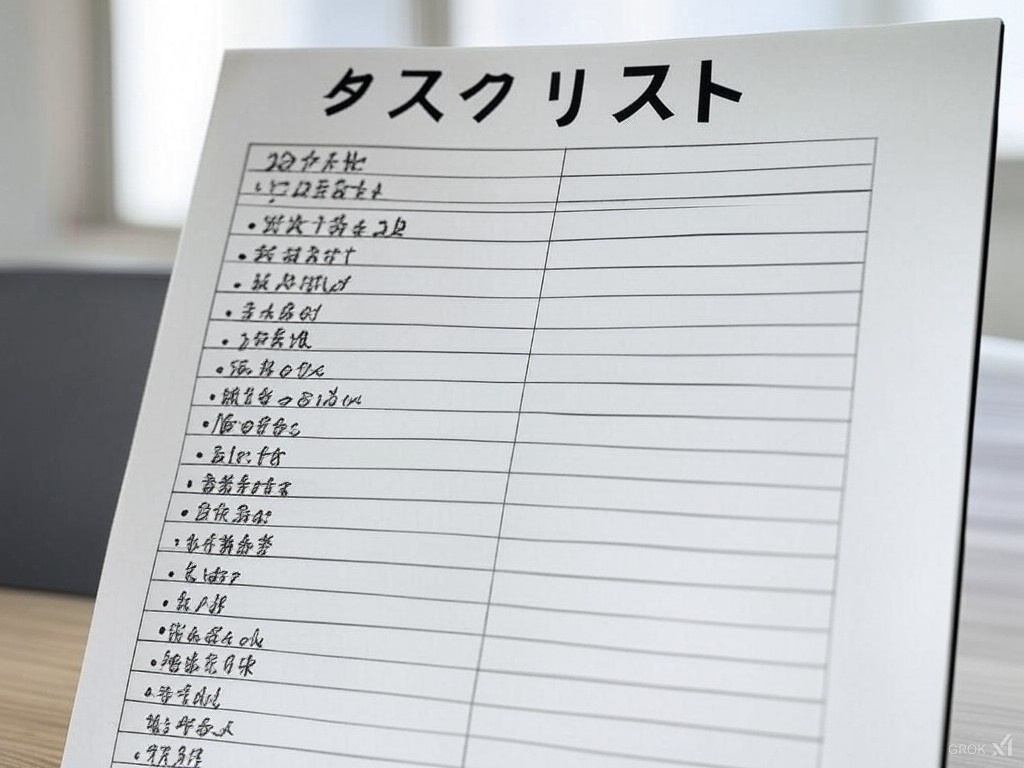「今日はこのタスクをやろう」と決めて、いざ実行しようとしても、
設定したタスクの抽象度が高すぎると何から着手していいかわからなくなるので、
できるだけ具体的なタスク名にすべきです。
例えば、こんなタスク。
「セミナーの骨子を検討する」
……ものすごいざっくりしていますよね。
実はこれ、私が今日設定してしまったタスク名なんです。
こんな名前にしてしまったばっかりに、残念ながらタスク実行に着手できず、
しょうがないので設定していた時間を他のタスクにあてることになりました。
ここから読み取れる情報としては「セミナー」と「骨子」と「検討」。
でも、「セミナー」のテーマは?「骨子」は何をもとに組み上げるのか?
「検討」とは具体的にどうすることなのか?ということが明確にならないと、
タスクの設定としては十分ではありません。反省でした。
もっと具体的にするなら、「先日クライアントと合意したセミナーテーマである
「●●」に関連して調達した書籍を読み、骨子に使えそうなポイントを
Onenoteに箇条書きで書きだしていく」といったところでしょうか。
(長すぎるので、わかる範囲でもっとコンパクトが望ましいですが)
これは人に指示を出すのも同じ。
育成目的などあえてそうする場合は別として、
指示を出すときも抽象度はできるだけ低いほうが、
指示を出される方も迷わずタスクを実行しやすくなります。
ご自身を振り返ってみて、抽象度の高いタスク設定や
部下・後輩への指示になってはいないでしょうか?
私も痛みを伴って学べたので、タスクを再設定して臨もうと思います。
~編集後記~
- 午前中はvFlat scanというアプリを使って書籍のPDF化を。分厚い書籍を片付けられたので、
本棚が少しすっきりしました。 - 午後はビックカメラへ。普段使っているBluetoothイヤホンが壊れてしまったので、
新しいものを調達しました。Airpodsのようなフルワイヤレスはなくしそうで怖いので
いつも選ばないようにしています。 - ご飯を食べてお腹いっぱい、だらっとしているうちの猫

【業務のご案内】
【SNS】フォローお願いします
- X(旧Twitter):会計・その他気づきの発信
- Instagram:日々の自己研鑽を発信
- note:旧ブログ。